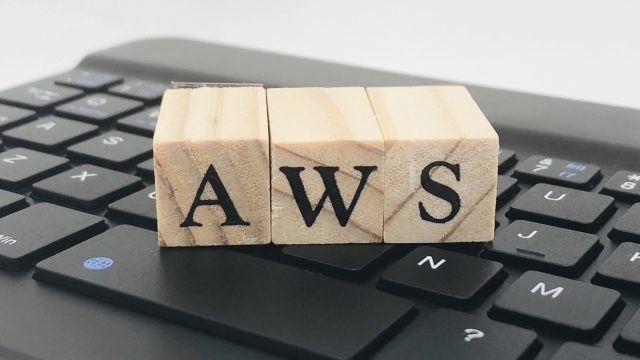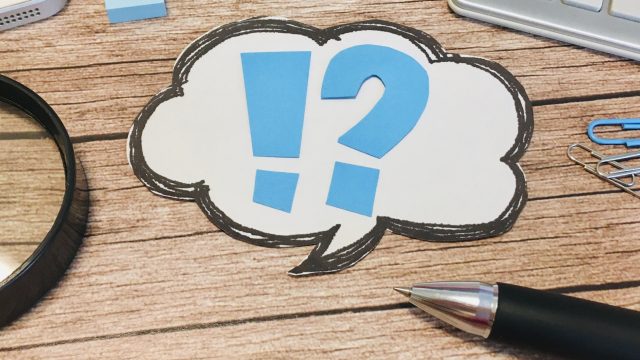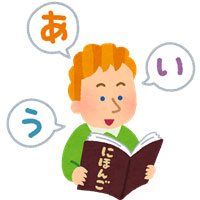友人から、結婚式の招待状が届きました。
挙式・披露宴は6月。
「そういえば、彼女、ジューンブライドに憧れていたね…」
でも、6月といえば、梅雨。
なぜ、わざわざ雨の多い6月に、結婚式を挙げるの?
▼目次(クリックで見出しへジャンプ)
ジューンブライドって何?
ジューンブライド(June bride)、直訳すると「6月の花嫁」。
欧米では、6月に結婚すると幸せになれるという言い伝えがあります。
なぜ、そう言われるのでしょうか。
そして、なぜ日本でもジューンブライドが知られるようになったのでしょうか。
ジューンブライド3つの由来
3つの説があります。
女神ユノーに由来
英語の6月「June」は、ローマ神話の女神「ユノー(Juno)」に由来しています。
ギリシア神話に出てくる最高神ゼウスの正妻ヘラは、夫が浮気性だったため、良い家庭を築き守ろうと、努力しました。
そこからヘラは、結婚生活における女性の守護神と考えられました。
ギリシア神話は後にローマに影響を与え、ゼウスはユピテル(ジュピター)、ヘラはユノーと名前の読み方を変えて、ローマ神話に取り入れられてヨーロッパに広まってゆきます。
ユノーは6月に祭られる女神なので、6月に結婚すると、結婚生活の守護神ユノーに守られて幸せになれる、という考えが広まりました。
結婚解禁の時だから
古代ヨーロッパでは、農繁期の3~5月には、農作業の妨げになる結婚は禁止されていました。
結婚が解禁される6月は、当然、たくさんのカップルが結婚式を挙げ、幸せが満ちあふれる月となります。
だから、6月に結婚すれば多くの祝福を受け、幸せになれるとされました。
気候がいいから
ヨーロッパの6月は、日本とは違って、雨が少なく穏やかな気候です。
ですから、気候のよい6月は結婚に適しているとされました。
なぜ日本で有名になった?
しかし、6月といえば、日本では梅雨のシーズン。
農家にとっては、田植えも始まってこれから忙しくなる時。
花嫁衣装や婚礼家具が雨に濡れる心配もあります。
出席者は、雨の中、式服を着て行くのは大変。
どうひいき目に見ても、結婚に適しているとは思えませんね。
事実、日本では6月に結婚式を挙げるカップルは少なかったのです。
ホテルの経営戦略?
そこで、売り上げが減る6月に結婚式を挙げてもらえるようにできないかと、1960年代に、ホテルオークラの副社長が知恵を絞りました。
ヨーロッパのジューンブライドという風習を、日本での営業に活用しよう、と提案したのです。
この戦術が的中して、「ジューンブライド」という言葉が日本にも根付くこととなりました。
ジューンブライドは、バレンタインデーと同様に、企業が主導して日本に取り入れられたのですね。
まとめ
- ジューンブライドが幸せになれると言われたのには3つの説がある。
- 1.結婚生活の守護神、女神ユノーから
- 2.結婚解禁の月だから
- 3.気候が良いから
- 日本でジューンブライドが知られるようになったのは、6月に結婚式を増やしたいホテル業界の思惑による。
日本では、6月より、秋や春の気候の良いときに結婚式を挙げる人が多数派です。
何月に結婚しても、2人の愛情と努力があれば、きっと幸せですばらしい結婚生活を築いていけるでしょう。